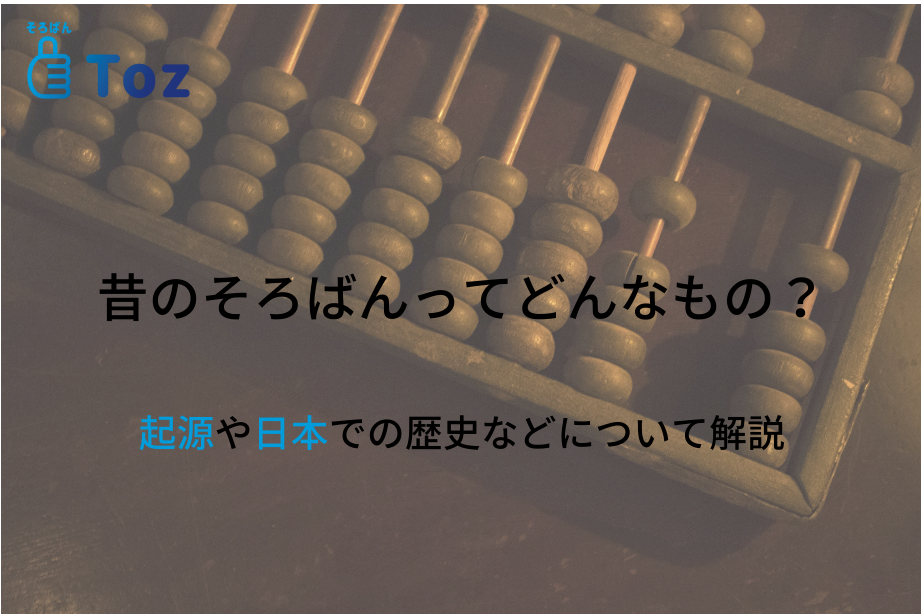世界最古のそろばん

多くの方が知っているようなそろばんが日本に伝来したのはおよそ16世紀頃とされていますが、世界で最も古いそろばんがいつ生まれたかはご存じでしょうか。現在発見されているそろばんの中で最も古いものは、ギリシャのサラミス島で発見された「サラミスのそろばん」と呼ばれるもので、紀元前300年頃のものとされています。
しかし、これはメソポタミア地方で作られたそろばんをルーツに持つものであり、いまはまだ見つかっていませんが、これよりも古くの時代からそろばんはあったとされています。
そろばんの歴史

| 年代 | 主な出来事 |
| 紀元前2000~3000年頃 | 砂そろばんの発明(イラク) |
| 紀元前500年頃 | 線そろばんの発明(ギリシャ・ローマ) |
| 紀元前300~紀元後400年頃 | 溝そろばんの発明(ローマ) |
| 14世紀 以降(1301~) | 中国でのそろばんの普及 |
| 16世紀以降(1501~) | 日本へのそろばんの伝播と普及 |
そろばんの起源
砂そろばんの発明(紀元前2000~3000年頃)
現在のそろばんの元となった「砂そろばん」の発祥地は、メソポタミア地方(現在のイラク)と言われていて、紀元前2000~3000年頃に文化民族と呼ばれるシュメール人(紀元前3000年頃、メソポタミア地方で都市文明を最初に生み出した民族)が計算をするために作ったのが始まりとされています。砂そろばんとは、現在のそろばんとは大きく異なり、ただ砂の上に石を置いて計算するだけのとても簡素なもので、作られた当時は現在の形とは遠くかけ離れていました。
線そろばんの発明(紀元前500年頃)
次に大きな変化が見られたのは、砂そろばんが生み出されてからおよそ1500~2500年ほど経った紀元前500年頃です。
この頃に「線そろばん」と呼ばれる新たなそろばんが発明されました。線そろばんとは、盤上に引いてある線の上に珠を置き、それを動かして計算するというものです。
現在のそろばんの、線上で珠を動かして計算する仕組みはこの発明によって生み出されたと言えるでしょう。
この頃から、ギリシャやローマなどでもそろばんが使われるようになり、特に西洋で普及し始めました。
溝そろばんの発明(紀元前300~紀元後400年頃)
ここから200年ほど経過した頃、「溝そろばん」というものが発明され、ローマでは、紀元前300~紀元後400年の間は、この溝そろばんが使われました。
溝そろばんは、線そろばんの線を溝に置き換えたもので、盤上に掘られた溝に珠をはめ込み、それを上下に動かして使われていました。そのため、この時代には、すでに現代のそろばんと似たような構造のそろばんになっていたと言えます。
中国への伝播
そろばんがいつ中国に伝えられたかに関しては現在でも多くの説があり、詳しいことは分かっていませんが、現在はローマからシルクロードを経由して伝えられたという説が主に支持されています。
中国でおよそ1700年前に書かれたとされる「数術記遺」(2世紀に徐岳(じょがく)が書いた文に6世紀頃、けんらんが注釈を加えた文書で珠算という計算法について書かれた算術書|中国のそろばん|日本珠算連盟 (shuzan.jp)より)には、上で述べた西洋の溝そろばんのようなものが書かれていたことから、この頃にはすでにそろばんの概念があったとされています。
しかし、そろばんが伝わった当時、中国では「算木」と呼ばれる計算用具が長く用いられ、生活に広く浸透していたため、そろばんは長い間ほとんど使われていませんでした。
14世紀頃にようやく、そろばんが普及しはじめ、17世紀頃にはそろばんに関する本が出されるなどして、算木ではなくそろばんを用いる計算が中国国内でよく使われるようになりました。
「数術記遺」に描かれていたそろばんは、現在のものと同じで木枠の中に梁があり、梁の上には5珠が梁の下には1珠がありましたが、当時は計算の都合上、現在のものと異なり、5珠が2つ1珠が5つの計7つの珠からなるそろばんが主流となっていました。
日本への伝播
日本へは、16世紀ごろに中国との貿易を行っていた長崎や大阪の堺に初めて持ち込まれたとされています。この当時、中国の貿易商によって持ち込まれたそろばんは当然現在とは珠の数が異なり、そのためしばらくの間は5珠が2つ、1珠が5つのそろばんがそろばんの基準となっていました。しかし、この頃そろばんが国内でどのように扱われていたかは分からず、1627年に書かれた「塵劫記」(中国の「算法統宗」という算術書を参考に吉田光由が書いた算術書)が国内で広く知られるとともに、そろばんも広く知られ、寺子屋などで使われるようになりました。
また後に、明治時代になって西洋の数学が取り入れられますが、それと同じくらいのタイミングで5珠が1つのものが増え、現在も使われているそろばんが主流となりました。
日本でのそろばんの歴史

ここでは、日本にそろばんが伝えられてからのそろばんの歴史について解説していきます。
室町時代後期~16世紀末
日本は16世紀頃、中国との貿易(日明貿易)を盛んに行っていて、当時貿易を行う港町であった長崎や大阪の堺に、初めて中国の商人たちによってそろばんが日本に持ち込まれました。
中国からそろばんが持ち込まれた当時は、国内で領主同士の戦いが多く起こっている時代であったため、そろばんは主に移動距離や移動時間を計算するためなどに使われていました。
江戸時代初期~江戸時代後期
江戸時代に入り、1627年に数学者の吉田光由によって書かれた書物「塵劫記」が広まるとともにそろばんは国内で広く知られるようになりました。
当時、庶民は農業を行っていて、普段から計算を行うようなことはありませんでしたが、「塵劫記」では数学の原理が分かりやすく説明されていて、また学びが重要視されるようになったため、庶民にも数学が広がります。そして、その機会に乗じ、「読み、書き、そろばん」を広く庶民に教えるため、国が多くの寺子屋(子供に読み書き、計算などを教える江戸時代の教育施設)を開きました。
明治以降
現在では、義務教育が当たり前となっていますが、明治5年になって学制が始まり、その8年後に教育令が出されたことによって初めて義務教育(小学3年生まで)ができます。当時、そろばんを授業に取り入れてほしいという意見が保護者など数多く寄せられたため、そろばんは学校での教育に取り入れられました。
戦後はまだ電卓などの計算機がなかったため、そろばん産業は最盛期を迎えますが、後に電卓やコンピュータが生産されるようになるにつれてそろばんの需要は減少し、産業は徐々に衰退していきます。
しかし、現在ではそろばんを習うことによって、右脳が鍛えられるなど、そろばんが子供の将来性を伸ばすことが分かったため、小学生の習い事として再び注目を集めています。
子どもの計算力×思考力×継続力を伸ばすなら|そろばんToz

驚愕のキャンペーン実施中!初月無料&そろばん+教材プレゼント
期間限定で、3つのキャンペーンを実施中です。
- そろばんを無料プレゼント
- 初心者用教材を無料プレゼント
- 初月無料でレッスンが受講できる
私どもが運営するToz(トズ)は、「子どもの無限の可能性を引き出す(Zレベルまで)」をコンセプトに、実用性のあるスキルと本質的なスキルとの両立を目指しています。
<こんなことでお悩みではありませんか?>
- 自分がずっと算数や数学で苦労してきたので子どもに同じ思いをさせたくない
- 子どもに集中力がなくて将来が心配…
- 子どもの才能を伸ばしたい
- 子どもに効率的に学習してほしい
- 子どもが算数に苦手意識を持っている
- 子どもに楽しみながらスキルを身に着けてもらいたい
そろばんを通して、これらの実用性のあるスキルを身に着けることができます。
- 知的好奇心
- 物事を素早く正しく読み取る力
- 数字に対する強さや慣れ
- 集中力
- 忍耐強さ
- 基礎的な処理能力
- 地頭力
さまざまなスキルが養われることにより、勉強に意欲的に取り組めたり算数に強くなったりします。勉強に対する苦手意識を克服し、自信をつけることも可能です。
実用性のあるスキルは、「中学受験合格」にも欠かせない素養です。昨今、中学受験のニーズの増加に伴い、受験体先の早期化が進行。大手学習塾に小学3年生から入塾する場合、入塾までに地頭力や基礎的な処理能力など、勉強の基礎となる能力を高めておく必要があります。
そろばんTozでは、今後、そろばん以外にも作文教室などのさまざまなサービスを提供予定です。
グローバル化・多様化が加速していく社会の中で、子どもが「自由に」生きるための素養を身に着けるためには、実用性のあるスキルだけではなく、本質的なスキルを学ぶことも大切だと考えています。そうした観点から、受験準備のみを想定してスキルを身に着けるのではなく、リベラルアーツ(教養)教育の側面も補い、自律的な考え方・生き方ができるようになっていただきたく願っています。
そろばんTozなら自宅学習がはかどる
そろばんTozでは、オンラインレッスン以外でも自宅学習ができるよう、無料で見れる動画教材を用意しています。動画では、「そろばんとえんぴつのもち方」や「たし算やひき算のやり方」などの動画を公開。そろばんでのたし方・ひき方がわからなくなってしまった場合や計算方法を確認したい場合など、ニーズに応じて活用できます。親御さんが動画を見ながらお子さんを指導する際にも、動画を利用すれば、正しい方法を指導することが可能です。
▼そろばんの動画教材一例
【関連記事】
こちらの記事では、そろばんが発明されてからどのように進化してきたかや日本にどのようにして伝わったかなどについて解説しています。